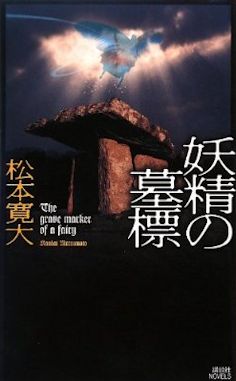 『玻璃の家』で第一回福山ミステリー文学新人賞を受賞し、衝撃的デビューを飾った作者の最新長編。あらすじはというと、名家の先代当主の死をきっかけに発生した連続殺人事件に『玻璃の家』の探偵が挑む、――ということになるのですが、この名家の事件と平行して読者の前に大きくクローズアップされているのが、画家の男が目にしたという妖精の謎。
『玻璃の家』で第一回福山ミステリー文学新人賞を受賞し、衝撃的デビューを飾った作者の最新長編。あらすじはというと、名家の先代当主の死をきっかけに発生した連続殺人事件に『玻璃の家』の探偵が挑む、――ということになるのですが、この名家の事件と平行して読者の前に大きくクローズアップされているのが、画家の男が目にしたという妖精の謎。
妖精や幽霊といった怪異の類いが本格ミステリの中に出てくれば、おおよそそれは幻覚か犯人のトリックや自然の産物によってつくりだされた偶発的産物というのが相場と決まっているわけですが、本作の場合は『玻璃の家』でも見せた科学的知見を加えて、妖精の正体というよりは妖精が生起するメカニズムを明らかにしていく展開がミソ。
とはいえ、海外在住の探偵が画家の過去を辿りながら妖精の謎解きをしていくというスタイリッシュな展開に平行して描かれる、名家の事件がやや冗長で、この重なりが妙にぎこちないところが個人的にはちょっとアレながら、ある意味定番の病気ネタが開陳されたあと、妖精が出現する上での引き金を探り当てていく中盤からの流れは素晴らしい。
当事者でありまた名家事件の謎解きを買って出た人物の推理から事件の構図が明かされ、そこからどんでん返しが見られるのはよいとして、名家の殺人事件の謎解きにおいては二時間サスペンスドラマのごとき愁嘆場が演じられるにいたって、高揚感は霧散してしまうという、――ダメミス的な意味での緩急が激しく、物語全体のリズムには最後までノることができませんでした。
このまま煮え切らないかんじでついに物語が終わってしまうのかと危惧していると、妖精の謎と名家事件とを連関させる事件の様相がエピローグで描かれていく結構はまさに掟破り。確かに探偵の推理によって妖精生起のメカニズムはすでに読者の前に提示され、様々の行動における動機も明かされているとはいえ、妖精を目の当たりにした人物の内心という心理的側面は依然として謎のままでした。ここで再びある謎が傍点付きで示され、真相がふたたび謎として反転するとともに、かの人物の絶望と死の恍惚を描き出した幕引きは暗い翳りを帯びつつも美しい。正直、このエピローグの壮絶と美しさだけで何だかすべての不満を帳消しにしてしまえるような気がするから不思議です。
謎解きに精妙な外連を見せた『玻璃の家』に比較すると、物足りなさや結構のぎこちなさが感じられるものの、個人的にはむしろ本格ミステリとしてよりは、エピローグの酷薄な美しさが際立つ幻想小説として愉しんだ方がいいのでは、――と思ったりもしました。しかしよくよく物語の全体を俯瞰してみると、後半に至るまでのぎこちなさともどかしさによってたまりにたまった鬱憤があるからこそ、この幻想的な反転が凄みを帯びているともいえるわけで、つくづく本格ミステリとは難しいんだなァ、……と感慨に耽った次第。
『玻璃の家』における二十一世紀本格の知見と外連を期待すると完全に肩すかしを食らうゆえ、取り扱い注意の一冊ながら、科学的知見によって描かれる幻想の美しさは貴重。むしろ好事家の方にこそ怖いモンみたさで手にとっていただきたい、そんな一冊といえるのではないでしょうか。
