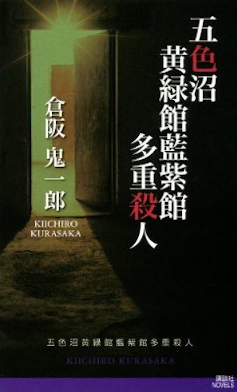 第二回島田荘司推理小説賞のレポートを書き終えてから、さて読書感想文に取りかかるかと身構えた矢先にひどい歯痛に悩まされること数日、昨日になってようやく親不知を抜いたものの、未だに何となーく鈍痛が続いているという状況なのがちょっとアレなんですが、まず新装開店ブログの感想文一冊目は、歯痛の中でヒーヒーいいながらも爆笑しながら読み終えたクラニーの最新作。
第二回島田荘司推理小説賞のレポートを書き終えてから、さて読書感想文に取りかかるかと身構えた矢先にひどい歯痛に悩まされること数日、昨日になってようやく親不知を抜いたものの、未だに何となーく鈍痛が続いているという状況なのがちょっとアレなんですが、まず新装開店ブログの感想文一冊目は、歯痛の中でヒーヒーいいながらも爆笑しながら読み終えたクラニーの最新作。
内容をバッサリと纏めてしまえば、ようするに訳アリな館に招かれた連中が次々と不可解な死を遂げて、――という例によって例による定番の結構を持ちながらも、ゴシックっぽい雰囲気は皆無。そもそもの館からして外壁が唐草模様で彩られているいう脱力ぶりで、思わずニンマリしてしまいます。
作者自身がバカミスを謳っている以上、こちらも苦笑と冷笑を交えて頁を繰っていくのが礼節というもので、序盤から「館の正体は何か――それはいずれ解明されるだろう」と、この館にもシッカリと仕掛けがありますよ、と作者自らがぐっと前に出ての自己主張で盛り上げてみせれば、世界の構造のと執拗に繰り返される内と外の概念が、この物語世界というよりは、小説そのものの根幹に大きく関わっているところも期待通り。
本作では過去作以上に性急な展開が見物で、物語が半分にも満たないうちから謎解きに突入という破格な結構にまず吃驚。数多の謎を繰り出して読者の興味を惹いてみせるという、謎のつくりに傾注した本格ミステリーの定番とは大きく異なり、なおざりなかたちでバカスカと駆け足で人死にを展開させ、すぐさまその殺人の謎解きを開始してみせるという破天荒さにもこれまたニヤニヤしてしまいます。
そもそもクラニーのバカミスでは、コロシのハウダニットの過程で脱力の舞台の謎と伏線の妙が明かされていくという趣向ゆえ、謎より何よりフツーの読者だったら気にもとめていないであろう舞台の仕掛けをザッと明かして読者を唖然脱力させてみせるという外連を、中盤から大きく展開させてみせた本作の構造は必然といえるのカモしれません。
とはいえ、本作の場合、操りやホワイダニットのあたりに、新本格の黎明期にはよく見られたあるネタを投入してみせたり、あるいは舞台の構造にもどこか既視感のあるネタがさらりと描かれていたり、さらには犯人が明らかにされたあとの探偵の逃走劇には、これまた過去作のネタを変奏してみせたりと、新作ならではの新味という点には乏しいのでは、――という感想を抱かれるバカミマニアの読者もいるのではないでしょうか。
しかしこうしたネタの変奏は、いうなればクラニーのファンサービスと見るべきで、作者ならではの文字に対する執拗なこだわりや、ブンガクというよりはもうこれって奇天烈な現代美術と同列に語った方がいいんじゃないノ、とツッコミを入れたくなる独特の趣向を仕掛けの中心に置くという「縛り」をもうけている限り、新味を狙うよりは、その徹底さ愚直さにおいて、いかに前作を凌ぐことができるかというところがキモ。クラニーのバカミスにおける新作は常にこうした評価軸から愉しむべき、と思うのですが、いかがでしょう。
で、そうした点から本作の到達点を見るに、その出来映えはどうだったのか、……結論からいうと、これは完全に「やりすぎ」(爆)。仕掛けが明かされた瞬間は、まとまった感想より先に、「ご苦労様」という言葉しか湧いてこない脱力の真相も見事なら、ご丁寧に頁数までシッカリと添えながら、シツコイくらいに説明がくわえられるその仕掛けの徹底ぶりにはもう脱帽。
過去作では、指定された頁に戻りつつ、なるほどなるほどと頷いていたわけですが、本作の「やりすぎ」ぶりはハンパではなく、ぶっちゃけ「読み返す」というよりは(以下文字反転)、パラパラ漫画みたいにページをざーっとめくっていくだけで、作者の執拗なこだわりと仕掛けが一目瞭然と明かされる趣向は、クラニーのバカミス史上、究極ともいえるのではないでしょうか。
さらに本作では、いつになく自己主張が強く感じられる作者の心意気が爆発して、最後の最後には作者そのものが神のごとく作品そのものを崩壊させてしまうという、大きく脱力の方向に振り向けた大ネタとともに、館に残された最後の謎を解き明かしてみせるという見せ方も素晴らしい。
既視感を覚えるネタが中盤までは添えられていながらも、その徹底ぶりは過去作を遙かに上回り、また最後の最後に明かされる真相の衝撃度という点でもまさに極北を体現した本作、クラニーのバカミスは最新作が常に最脱力という期待を裏切らない逸品ゆえ、自分のようなファンであればもちろんマスト、――とはいえ、その極北を目指した破天荒な風格は、「バカミスってよくわかんねーけど、どんなもんなの?」というビギナーには「だからどうしたの?」の一言で済まされてしまうというきらいもあるゆえ、そうしたノーマルな方々にはあくまで取り扱い注意、ということで。
