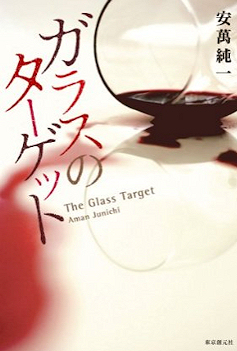 「第二十回鮎川哲也賞受賞作」の処女作『ボディ・メッセージ』は、海外を舞台にしたスタイリッシュな雰囲気のなかにキワモノ風味の仕掛けがキラリと光る逸品でしたが、今回の舞台は日本。それも八王子だ町田だと個人的には微妙にローカルなところがちょっとアレ(爆)。
「第二十回鮎川哲也賞受賞作」の処女作『ボディ・メッセージ』は、海外を舞台にしたスタイリッシュな雰囲気のなかにキワモノ風味の仕掛けがキラリと光る逸品でしたが、今回の舞台は日本。それも八王子だ町田だと個人的には微妙にローカルなところがちょっとアレ(爆)。
物語はイキナリ豪快な爆破事件から始まり、二つの集団毒殺事件に探偵への挑戦状と、現代的な大量殺人と古風な趣向を混淆させた風格ながら、物語の展開は警察が被害者の関係者を淡々と当たっていくも手がかりなし、いったい犯人は何奴……というふうに悶々としているうちにまた次の事件が起こって、――というふうに捜査のシーンが続いて読者がそろそろダレてきたかな-、というところでまた事件を引き起こして興味を惹きつけておくという懐かし風味溢れる結構ながら、ようやく探偵が登場した後半の展開は魅力的。
警察の捜査ではまったく犯人の正体を捕捉できなかったのが、探偵の視点によって三つの事件を俯瞰するとアラ不思議、意外なほどにするすると犯人像が炙り出されてくるという外連はややもするとやりすぎに思えてしまうのですけれど、もともとが天才型ということで通っている探偵ゆえ、このあたりは古風を活かした探偵小説として愉しむのが吉、でしょう。
個人的にもっとも惹かれたのは、やはり探偵の視点の鋭さと推理の端緒の見せ方で、爆弾を使った集団殺人に、二つの毒殺事件とあるなかで、特に後半の二つの毒殺事件では第一の犯行ともいえる爆殺との比較ではなく、連続毒殺事件の相違に着目した推理から、第三の事件の特殊性を繙いていき、この第三の殺人の動機の明快さを逆算していくかたちで本丸ともいえる前の二つの事件の真の動機を探っていく手際が素晴らしい。
ハウダニットやそれぞれの事件の様態は極めて既視感のあるものながら、そこへ探偵の鋭い気づきを添えてみせることで、全体の構図を際立たせてみせたところに、事件の「型」を作り出す作者のうまさが見られます。とはいえ、上にも挙げたとおり、その「型」を物語として展開させるところは、警察側の捜査を繰り返し繰り返し描きつつも結局成果なし、で、そろそろ読者がツマんないと感じてきたところで再び事件をブチこんで、――という、かつての推理小説みたいな趣が感じられるゆえ、このあたりは一分一秒たりとも時間を無駄にしたくない現代人には評価の分かれるところカモしれません。
犯人はやや意外というか、結構大胆に読者の前に姿を現していながらも、その存在を気取らせないために探偵との関わりをこうしたかたちにしたのか、とそのうまさに感心しつつ、探偵が登場するまでは関係者を調べても成果なし、を繰り返してノンビリ展開していたのとは裏腹にかなり慌ただしく「え、これで終わり?」と思わせる口ポカンな幕引きにはチと吃驚。
総じて、結構と展開の中に古さと新しさの双方を織り交ぜた作風は、海外を舞台にしたキワモノ風味という前作と同様、そのギャップに作者ならではの癖を感じさせる佳作でありました。前作のようなトリックを期待するとアレですが、推理の端緒となる探偵の鋭い視点など、処女作に見られた魅力は健在ゆえ、そうしたものを所望の読者であればなかなかに愉しめるのではないでしょうか。
