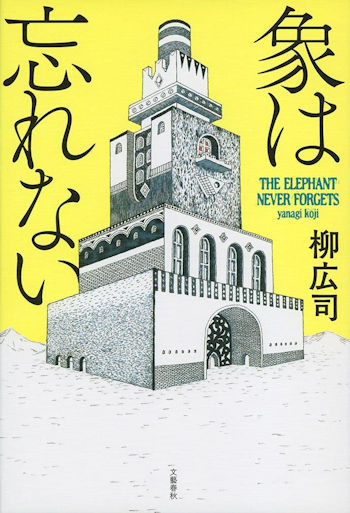 まず最初に書いておくと、本格ミステリーではないです。ジャケ帯には「ミステリーの旗手・柳広司による、物語でしか描けなかった、あの震災と原発事故。」とあり、タイトルにはクリスティのあの作品と、「象」に「原発事故」という引用からチェルノブイリの”アレ”をイメージしてしまうのですが、実はどちらも大きな繋がりはありません(ないと思います)。ミステリーではないからつまならなかった、というと、そういうわけでは決してなく、なかなか愉しめました。ただ読後感は、……というあたりについて後述します。
まず最初に書いておくと、本格ミステリーではないです。ジャケ帯には「ミステリーの旗手・柳広司による、物語でしか描けなかった、あの震災と原発事故。」とあり、タイトルにはクリスティのあの作品と、「象」に「原発事故」という引用からチェルノブイリの”アレ”をイメージしてしまうのですが、実はどちらも大きな繋がりはありません(ないと思います)。ミステリーではないからつまならなかった、というと、そういうわけでは決してなく、なかなか愉しめました。ただ読後感は、……というあたりについて後述します。
収録作は、安全神話と先端科学による輝かしき未来を信じていた原発作業員が経験したあの日の絶望「道成寺」、あの日に助けることのできなかった女の声に苛まれる男の悔恨がやるせない悲哀を誘う「黒塚」、あの日から生活が一変し、”真実”の狭間で翻弄される女を描いた「卒塔婆小町」、トモダチ作戦の背後で隠微に進行していた出来事を、ある男のセラピーによって暴き立てるおぞましき一編「善知鳥」、お上の曖昧至極な方針によって翻弄され、引き裂かれる日常と友情「俊寛」の全五編。
巻末にある「初出」によれば、「善知鳥」を除く四編が『オール讀物』に掲載された短編とのことなのですが、確かに「善知鳥」だけはやや風合いが異なります。さきほど本作は本格ミステリーではないと書きましたが、この「善知鳥」だけは、ある事柄の背後で進行していたもう一つの出来事を暴き立てるという趣向においてはミステリーといってもいい一編なのですが、他の四編が、我々読者がいる「内側」を描いているのに対して、この「善知鳥」だけは「外側」から福島ならぬフクシマを描いている点でもやや趣を異にします。
「善知鳥」は全編これすべて、メリケン男とカウンセラーとの会話のみで成り立っている物語なのですが、話が進むにつれて、この主人公であるメリケン男は、件の「トモダチ作戦」に参加した人物であり、この作戦遂行によって心に深い傷、いわゆるPTSDを負っているということが判ってきます。しかしながらこの人物は軍の中でもメンタルが強いと評価されてい、過去様々な作戦の中でもマッタク問題がなかったらしい。ではなぜ今回トモダチ作戦に参加したことで心の深い傷を負うことになったのか、――というホワイダニットの謎が読者の前に提示されるものの、このホワイダニットの展開に伏線からの推理といった趣向は薄く、淡々と物語は進んでいきます。トモダチ作戦の背後で隠微に進められていたおぞましきもう一つの作戦の内実は静かな怒りを誘い、さらにはだめ押しとばかりにそのトラウマ治療を行うにあたってセラピストが提案した妙案というのが、我々日本人であれば誰もがあきれ果てたであろう、ある事実を元にしており、読後感は正直胸くそ悪いことこの上ない(苦笑)。マトモな日本人であれば、メリケン野郎に殺意を抱くこと間違いナシ、という殺傷度の高い一編といえるでしょう。
「道成寺」は、原発に懐疑的だった恋人と、原発作業員としての自分の仕事に誇りを持っている主人公との対比から始まり、それがあの事件によって一気に絶望の淵へとたたき落とされる流れが悲哀を誘います。
「黒塚」は原発事故によって何度もの避難を余儀なくされた住民の一人を描いた物語で、ガイガーカウンターを持っていたばかりにそれが裏目となって、悪い方へと転じてしまう変転が哀しい。しかしながら、避難所に留まっていた主人公と友人たちの選択を間違っていると、いまの読者であれば誰も責めることはできないのではないか、――そんな沈んだ思いに心が真っ暗になる憂鬱な一編です。
「卒塔婆小町」もまた原発事故後、情報の錯綜に翻弄される主人公がやるせない。何が危険で、危険でないのか、という情報の奔流から逃れた彼女の選択と着地点が”そこ”だったのか、そこしかなかったのか、というところが哀しい。
「俊寛」は、仲間たちの住んでいた地域が少し離れていただけで避難地区であるか、ないかに分かれてしまうという不条理を引き金に、それぞれの選択と別れを描き出した一編なのですが、これもまた読後、ちょっと暗い気持ちに沈んでしまいます、――というわけで、全編爽快さもマッタクない、読むとかえって暗くなる、そしてメリケン野郎や政府に対する怒りが湧いてくるという何とも一冊なのですが、しかしなぜ『新世界』という傑作を描いた「ミステリーの旗手」である作者が、本作を本格ミステリーにしなかったのか。それは”敢えて”そうしなかったのか、あるいは”できなかったのか”……。作者の技量を鑑みれば、このテーマを元に優れた本格ミステリを描くことも不可能ではなかった筈で、あるいはそれは、自分たち日本人にとってはいまだあまりに生々しいテーマであるがゆえに、本格ミステリーという”娯楽”作品にすることを忌避したのか、……と自分などは穿った見方をしてしまうのですが、実際はどうだったのでしょう。――などと考えてしまったのは、当然、谺健二氏の三部作が頭にあるからなのですが。
個人的には本作のもやもやとした読後感を払拭してもらうため、是非とも柳氏には、この主題に内在される呪詛を本格ミステリーという堅牢な石棺によって封印し、我々日本人が悲哀の中からささやかな希望を見出せるような物語を、”本格ミステリー”の続編として描いていただきたいと願ってやみません。そう、あの『赫い月照』のような超絶的な作品を――。
というわけでかなり読後感は悪いものの(苦笑)、その一方で、今読むべき物語である、という気もする本作、小説に快楽を求めるカジュアルな読者にはなかなかにヘビーな一冊ゆえ、このあたりは取扱注意ということで。
