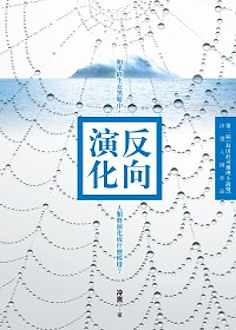 前回が第二回島田荘司推理小説賞関連の作品(林斯諺『無名之女』)だったので、今回はその絡みで、冷言の『反向演化』を取り上げたいと思います。本当は昨年の今頃に紹介しておくべき一冊だったのですが、まあそこはそれ、ということで。
前回が第二回島田荘司推理小説賞関連の作品(林斯諺『無名之女』)だったので、今回はその絡みで、冷言の『反向演化』を取り上げたいと思います。本当は昨年の今頃に紹介しておくべき一冊だったのですが、まあそこはそれ、ということで。
本作は、第二回島田荘司推理小説賞の入選作の一編で、冷言の長編作品としては『上帝禁區』、『鎧甲館事件』に次ぐ三作目ということになります。登場する探偵も冷言で、おまけに登場人物も『鎧甲館事件』で主要な役割を果たした人たちが出演しているということもあって、できれば『鎧甲館事件』を読了したあとの方が、登場人物たちの逸話も含めていろいろと愉しめたりするのですが、本筋を追うだけであれば、未読であっても没問題。
物語は、探偵事務所を訪れたアイドルの娘っ子から、とある不思議写真を見せられるところから始まります。沖縄にほど近いある無人島で昔に撮影されたその写真には、仄暗い洞窟からヌーッと顔を覗かせた人外の姿が写っている。果たしてこれは何なのか――。実はこの娘っ子はとあるロケの仕事で、件の島に赴くことになっているのだが、それをやめろという脅迫状が”地底人”の書名で彼女の元に届いている。冷言は彼女からの依頼で、件のロケに参加することになるのだが、――という話。
ちなみにその島には地底人が潜んでいるという伝説があり、件の地底人の正体を探ってやろうというのが件のロケの目的で、第二回島田荘司推理小説賞授賞式の後に誠品書店で開催された御大とのトークショーに曰く、「『水曜スペシャル 川口浩 探検シリーズ』のDVDを徹底的に研究し尽くした」という地底洞窟の描写は圧巻で、本作は人外の謎に正体不明の人物からの脅迫状という、古典本格らしい定石を物語の骨格に据えながらも、前半を過ぎてからの展開は香山滋や橘外男などを彷彿とさせる作風で魅せてくれます。
後半の謎解きになだれ込むまでの秘境小説めいたシーンがあまりに長いがために、中には本作を本格ミステリではないと感じる読者もいるかもしれません。実際、本作の刊行当時、冷言氏は知人の一人から「これは本格ミステリじゃない」という指摘を受けたという話を耳にしたのですが、本作が秘境小説に『擬態』しているのには、もちろん理由があります。
これは前回の『無名之女』にも共通するのですが、リアリズムに徹した本格ミステリである限り、「地底人はいるのか、いないのか」という問いに答えはひとつしかありません。本作ではこれを打破するために秘境小説的な作風が敢えて採られたのだということがその理由のひとつとしてあるわけですが、それ以上に、本作に描かれる不可能状況の仕掛けを隠蔽することが挙げられるでしょう。
本作では”本格ミステリらしく”、当然多くの人死にがあるのですが、そのほとんどには秘境探検であれば必然ともいえる事故の類いが絡んでい、そうした必然的状況の背後に地底人の真相へと繋がる伏線を忍ばせてある技巧が心憎い。
しかしやはり本作最大の眼目は、この秘境ならではのある壮大な仕掛けであり、このトリックは幽霊や脅迫状などから想起される古典ミステリの規則からはほとんど反則すれすれの大技でもあります。しかし秘境小説への擬態は、本作を本格ミステリとして読むことによって必ず生じるであろうそうした批判を無効化し、同時にこの壮大な大仕掛けを物語の中の必然とする機能をも担っています。
そうした視点から本作を再読すれば、本格ミステリとして読むことによって生じる違和感から「この作品は本格ミステリではない」という感想を持たれるのはいわば当然ともいえます。現代本格が別の形式に擬態する技法には様々なバリエーションがありますが、たとえば傑作『遠海事件』のように、小説では”ない”他のものに擬態しているときには、擬態そのものを読者が意識できるがゆえに、読了後はこの擬態が技法のひとつであることを容易に了解できるわけですが、本作のように小説の別ジャンルとして――さらには、それが本格ステリの源流にも繋がるであろう香山滋や橘外男のような作風の秘境小説だとすると、これが本格ミステリの技巧としての擬態であることには読了後も気がつきにくい、……というか、読了後も気がつかないことも十分にありえます。
一読すると、古き良き時代の探偵小説を思わせるくすぐりを鏤めながら、その実、そこで使用されている壮大な仕掛けは、御大の『水晶のピラミッド』などを彷彿とさせるものの、しかし御大の作品では、不可能状況はクローズアップされ、物語を牽引するための謎として鋳造する方法であるのに対して、本作ではむしろこの壮大な仕掛けそのものを隠蔽するために、あえて表層に見える謎を小さな殺人に極小化しているなど、そのアプローチは異なります。
この壮大な仕掛けは最後の最後に地底人の謎と見事に共鳴して物語は幕となるのですが、惜しいナーと思うのは、もしこの物語が『水晶のピラミッド』ではなく、『ハロゥウイン・ダンサー』の技法によって書かれたらどうなっていたかということで、さすれば本作は『無名之女』と並ぶ21世紀本格になっていたのではないか、――などと夢想してしまいました。いかにも続きがありそうな最後の一行でパンチを効かせた終わり方を見せる本作には、是非とも続編を期待したいと思います。
