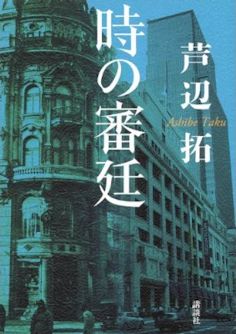 大問題作。『綺想宮殺人事件』以上に、”現実との格闘”の痕跡がうかがえる本作、自分は『時の』シリーズの最新作として、というよりは、『綺想宮殺人事件』を経て傑作『スチームオペラ』へと辿りついた作者の最新作として堪能しました。
大問題作。『綺想宮殺人事件』以上に、”現実との格闘”の痕跡がうかがえる本作、自分は『時の』シリーズの最新作として、というよりは、『綺想宮殺人事件』を経て傑作『スチームオペラ』へと辿りついた作者の最新作として堪能しました。
物語は、総選挙の当日に震災が発生したとの報道があり、探偵森江のもとには奇妙な電話がかかってくる。ハルビン編ともいえる過去の部においてもまた、戦後の某事件を彷彿とさせる殺人事件を追いかけていた記者のもとに、友人から不可解な報せがあり、――という話。
過去と現在を交錯させ、それがひとつに繋がっていくという結構は、『時の』シリーズではお馴染みながら、本作では冒頭に作者からの「――これは架空の物語です」から始まる奇妙な序文が添えられているところに注目でしょうか。これまた芦辺小説ではお馴染みの「あとがき――あるいは好事家のためのノート」ではなく、物語が開幕する前に「もとより小説とは、それ以外の何ものでもないわけですが、執筆に三年余りを費やした本作品に関しては、あえてそうおことわりしないわけにはいけない事情があるのです」と書かれているのには大きな理由があり、このことを考慮に入れてその先に進むか、進まないかによって本作の評価は大きく変わってくるような気がします。
ハルビン編ともいえる過去のパートと、現在のパートを表層において連関させ、一つの謎として物語を牽引していくのが「日本分断」という奇妙な言葉になるわけですが、本作においては、作者が冒頭で断り書きをしている”ある事実”によって、本作を”ただの”架空の物語として読み進めていくか、それとも現実との接点をもった、――「もうひとつの現在」の物語として読み進めていくかによって、読後感は大きく異なるかもしれません。ましてや、作者は虚実の交錯を十八番とした作風で多くの傑作・問題作をものしてきた芦辺氏のことですから、序編が掲載されたあと、作者と読者が依って立つこの現実世界において発生した「横なぐりの痛烈な鞭」のごとき出来事を、物語の続きにおいてどう受け入れ、処理していったのか、――そのあたりが気になってしまうのは必然でしょう。
『虚無への供物』以降、日本の本格ミステリ作家は、現実との格闘と超克を強いられてきたわけですが、本作で、芦辺氏は『グラン・ギニョール城』を起点とする虚実の接点を調律する技巧によって、ハルビン編に鏤められた様々な事件を作中の現実と結びつけ、最後には我々読者が依って立つこの現実の皮相さを皮肉りつつ、おぞましい陰謀劇を虚構へと反転させる荒技によって現実を”超克”するのではなく”調伏”してみせます。
ハルビン編における伯爵一家の失踪や、電話ボックスでの不可解な密室殺人というおのおのの事件に付与されたトリックは、いかにも本格ミステリ的ともいえるものなので良しとして、賛否両論分かれそうなのが、探偵森江曰く「史上最劣にして最恐」の密室のトリックでしょう。これは上に述べた荒技を達成するためにも決して欠かすことのできない掟破りの技巧だったりするわけですが、これがあるからこそ、過去編における二人の人物がこの「史上最劣にして最恐」のトリックを用いることのできる”犯人”に対して抗おうとした行動と、その後の運命の相違が際だっているともいえます。
したがって「史上最劣にして最恐」の密室トリック”そのもの”だけを抜き出して云々するのは本作に限れば御法度で、ここはハルビン編と森江たちのいる現実世界が交錯を見せる後半、かれの推理の過程で明かされていくこの二人の人物の悲運をドラマチックに盛り上げていくための装置として堪能するのが吉、でしょう。
本格ミステリ的な外連としては、冒頭で描かれるあるシーンが、謎解きによって過去と現在の事件を結びつけ、二重、三重写しの真相を描き出していたことが明かされる見せ方が素晴らしい。奇想天外な電話ボックスのトリックなど、「「史上最劣にして最恐」の密室以外の仕掛けは『時の』シリーズどおりの安心して愉しめるものです。
とはいえ、戦後の闇を彩る二つの事件を模したとおぼしき大事件が、本作で描かれる陰謀劇に深く関わっていること、その人物もまた現実世界のあるものを想起させること、さらには序編で語られるある出来事など、読者としてはやはりどうしても我々が依って立つ現実に引き寄せて考えてしまうのもまた事実で、いつもの芦辺節でありながら、現実世界との接点を孕んだどこか不穏な雰囲気を感じてしまうところは異色作、といえるかもしれません。作者に対しては、序編を書き終えたあとの現実世界からの鞭に耐えて、よくぞ書き切った、――という思いが個人的には強いのですが、虚実の交錯によって物語を紡いできた作者が、現実世界からの襲撃に対してどのような外連と超絶技巧によって、この呪いを”調伏”してみせたのか、そして架空のものへと還元された物語はどのような美しき幻想へと収斂していくのか、――ここは是非とも実際にこの物語を体験して確かめていだければと思います。
『綺想宮殺人事件』以降の作品としては、間違いなく作者の代表作として記憶されるべき一冊であり、またいままで氏の作品を追いかけてきたファンであれば、かなりの覚悟をもって挑むに足りる力作といえるのではないでしょうか。オススメです。
以下はオマケ。総選挙だ大地震だという話が出てきて、さらには下山事件や帝銀事件を彷彿とさせる戦後の闇の話が出てくるものだから、『時の』シリーズの最新作で森江が出てくるといっても、これらはすべて平行世界でのお話であって、今回は過去と現在を重ねる二重構造をさらに発展させ、過去と現在に平行世界を重ねた三重構造の物語なんじゃないかナ、――なんて考えてしまったのはナイショです(爆)。だって、『スチームオペラ』のあとですよ? そんなおとぎ話を今の芦辺氏が書いたって不思議ではない、……と考えてしまったのは自分だけではないと思うのですが、いかがでしょうか。
それともう一つ、講談社の特設サイトでは「著者のメッセージ」として、本作を「伝奇時代小説」としていますが、個人的には半村良の「伝説」シリーズのような伝奇ロマンを思い出しました。つまりは本作、個人的には大好物だったということですね。
