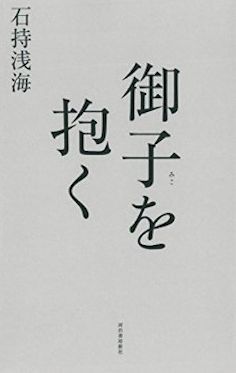 石持氏の新作長編は結構な長さにしてはエロジックもナッシングという地味さながら、常識の斜め上をいく気色悪さはピカ一。そもそもジャケ帯からして「私は正しい私は正しい私は正しい」と某新興宗教のキ印マントラを想起させる同じ言葉の連打にタイトルが「御子を抱く」。冗長さを除けば、登場人物たちの気色悪さをネチっこく、また瑞々しく描き出した、――まさに作者でしか書き得ない逸品といえるカモしれません。
石持氏の新作長編は結構な長さにしてはエロジックもナッシングという地味さながら、常識の斜め上をいく気色悪さはピカ一。そもそもジャケ帯からして「私は正しい私は正しい私は正しい」と某新興宗教のキ印マントラを想起させる同じ言葉の連打にタイトルが「御子を抱く」。冗長さを除けば、登場人物たちの気色悪さをネチっこく、また瑞々しく描き出した、――まさに作者でしか書き得ない逸品といえるカモしれません。
あらすじは、ジャケ帯に添えられた文章をそのまま引用すると「閉鎖的なコミュニティに渦巻く猜疑と羨望と歪な正義は、あの日殺意に変わった」とあるのですが、これは精確にいえば読者の誤導を狙った間違いアリの内容ゆえ、軽くスルーしておくのが吉、でしょう。一応、物語は、新興宗教の教祖の素質アリな男に魅了された凡人たちが、八番街という場所に次々と引っ越してきて「コミュニティ」をつくっていた。しかし彼の死によって、「門下生」たちは「コミュニティ」の跡目相続を狙って疑心暗鬼に陥っていた。そこへある重要人物が不慮の事故に遭ったことをきっかけに連続殺人劇が始まり、――という話。
ジャケ帯には「閉鎖的なコミュニティ」とありますが、一応、皆はフツーに会社勤めなどをしている凡人ばかりゆえ、出家や家出をした信徒たちが「閉鎖的な」暮らしをしているような様態とはやや異なるゆえ、このあたりについてはゆめゆめジャケ帯の文章は惑わされないよう。しかし逆にその「閉鎖的」でないところが本作のキモで、ごくごくフツーに見える人間たちが、一人の男に対して崇拝にも似た気持ちを抱いているというだけでもかなりアレなのですが、さらには彼の近所に次々と引っ越してきて共同体を形成している、――となるとこれはもうホラーの舞台になるほどに薄気味悪く、またその人物の子供を「御子」と呼んでいるあたりはもう完全にキ印ワールドに片足を突っ込んでいるようなもの。
本作の場合、この一見普通に見えながら、宗教とも異なる奇妙な共同体という舞台装置が秀逸で、新本格からこっちの現代本格においては、こうした背景に明快な新興宗教などを採用して異世界の雰囲気づくりに徹するところが、敢えて我々一般の読者が住んでいる世界と地続きの新興住宅地を物語世界に据えたところが秀逸です。
本作の探偵は、この共同体の外部からやってきた人間で、そのあたりは上にも述べたような、新本格以降の定番的な作風と異なるところはありません。この探偵役の人物は、ある人物の死から重要な立場にたたされることになる女性と知り合い、それをきっかけにこの事件へ首を突っ込んでいくことになるわけですが、物語のシーンの一部は、この女性の視点から語られていきます。こうすることで、この女性が探偵役の男性に抱く仄かな恋愛感情、――とはいえ、そこは石持氏の作品ゆえ、その描写は恋愛に対する態度もかなり斜め上を行く感覚ではあるのですが、――を読者は登場人物たちとともに共有することになります。しかしいこれが探偵の推理にいたって、精妙な伏線であったことが明かされるところが素晴らしい。
この探偵役の人物のほか、「御子を抱」いてコミュニティの力学関係に変化を起こそうとする連中たちもね、件の殺人事件の犯人探しを行っていくのですが、コミュニティの仲間が次々と殺されていくところから、当然、これらの犯行は「内部」の門下生の仕業だろうと彼らが考えることは当然至極。そしてこの推理の起点と方法について、登場人物の台詞を引用してみると、
記憶の中からそれを探しだし、実際の生活に活かていく。それが門下生のやりかただ。教えに対する今後のに取り組み方が違っても、行動は共通していると思う。
すなわち、門下生が犯人であるとすれば、自分たちは「教祖だったらこんな状況においてはどんな判断をし、どんな行動を起こすだろう」と考えるわけで、その意味では、敬虔な信徒といえる門下生であればあるほど、必ずその推理の終点は同じになる筈です。本作では、フェアプレイに徹するため、章の要所要所に「間章」が挿入され、そこでは門下生たちが「教祖」然とした人物と出会ったときの逸話が披露されています。
これを読むと、自分のような凡夫は「こんなちっぽけなエピソードでガツーンとやられてしまうってヤバくない?!」などと苦笑してしまうのですが、登場人物たちは大真面目。このあたりの「ずれ」や「違和感」は、石持ワールド特有の魅力としてあまり深くは考えず、ひとまずこうした逸話の連なりから、読者は教祖様の思考パターンを敷衍しながら門下生たちの行動を推理していくことになるのですが、これがまた最後の最後、巧妙な誤導へと転化する技法がタマりません。
異世界ものにおける異世界の論理の物語の外観を持ちながら、それがある真犯人像の隠蔽であったことが明かされる真相に驚きは薄く、――というのも、異世界ものを期待しながら、それを裏切る事件の真相は、「尻すぼみ」に感じられてしまうからなのですが、しかし真相そのものではなく、上に述べた物語世界の擬態と反転、さらにはそれを用いて真犯人を容疑の埒外に隠蔽してしまう技巧そのものに眼を向ければ、本作がこれだけの長さを持つのも必然であったことが納得でき、またその長さを費やして作者がいかに大胆なミスディレクションを構築みせたのか、――このあたりも十分に腑に落ちて満足の読後感を得られるのではないでしょうか。
個人的には最近の石持ミステリの中では、エロミス度数も大薄で、せいぜい登場人物の一人が「全身をナメクジが這い回るような恐怖を覚える」といった描写に、「生真面目な河出書房からのリリースゆえ、精液愛液の代わりにナメクジの体液をイメージすることで今回は勘弁仕り候……」なんていう作者のささやかなエクスキューズを感じるところや、ヒロイン役の初な女性がある人物のたちセックスを妄想して動揺するシーンを後半に用意するなど、ところどころに石持ワールドの「らしさ」は垣間見えるものの、エロの濃度は控えめも控えめなのでそのあたりを期待するのは御法度でしょう。とはいえ、斜め上を行く登場人物たちの思考を愉しめるという点では、「石持ミステリでは、『セリヌンティウス』が一番好き。だから、だから、みんな一緒だよっ!」なんてセカイ系女子(?)を射程に据えた一冊といえるのカモしれません。まあ、エロに関しては文藝春秋から近々刊行される『相互確証破壊』に期待するといたしましょう。
